 農地コラム
農地コラム 家庭菜園に関係する法律とは、どんな罰則があるの?農地付き住宅で家庭菜園
農地法の農地利用の条件 地方での田舎暮らしで、農家的な暮らしを楽しみたいという人も多くいます。地方の空き家には、以前の居住者が使っていた農地といっしょに貸したいという場合も多くあります。 地方の戸建の空き家では、農地の利用もいっしょにするこ...
 農地コラム
農地コラム  農地コラム
農地コラム  農地コラム
農地コラム  農地コラム
農地コラム  農地コラム
農地コラム  農地コラム
農地コラム  農地コラム
農地コラム  農地コラム
農地コラム  農地コラム
農地コラム  農地コラム
農地コラム  農地コラム
農地コラム  農地コラム
農地コラム  農地コラム
農地コラム  農地コラム
農地コラム  農地コラム
農地コラム  農地コラム
農地コラム  農地コラム
農地コラム  農地コラム
農地コラム  農地コラム
農地コラム  農地コラム
農地コラム 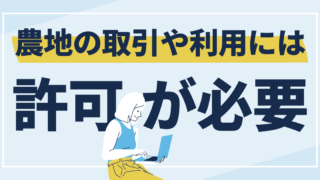 農地コラム
農地コラム  農地コラム
農地コラム  農地コラム
農地コラム  農地コラム
農地コラム  農地コラム
農地コラム  農地コラム
農地コラム  農地コラム
農地コラム 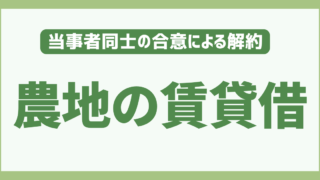 農地コラム
農地コラム 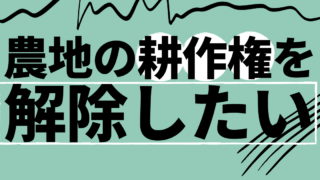 農地コラム
農地コラム  農地コラム
農地コラム